
「子供たちを来させなさい」 マタイによる福音書19章13~15節 2025年8月10日
2025年8月10日 主日礼拝(朝・夕拝)説教 「子供たちを来させなさい」
聖書―マタイによる福音書19章13~15節
(はじめに)
毎年8月は、私たちが住み、生きている日本という国にとっては、忘れてはならない出来事が起こった月です。6日は、人類初の原爆が広島に投下された日です。9日は、原爆が長崎に投下された日です。そして15日は、終戦記念日です。日本は80年もの間、戦争のない日々を歩んできましたが、それはこれからも続くとは限りません。毎週の祈祷会では、教会の皆さんと祈りを合わせていますが、その祈りの中で、平和を求める祈りが聞かれます。平和を求める祈り、私たちはこの祈りを絶やしてはなりません。
平和というと、よく知られている聖書の言葉の一つに、「平和を実現する人々は、幸いである、/その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5章9節)というみ言葉があります。平和というと、戦争がない、ということを考えますが、聖書が示す平和というのは、戦争がない、戦争をしない、というだけでなく、積極的に平和の実現のために励んでいくことです。互いのことを、神さまが造られ、愛される大切な存在として尊重し、共に生きることです。「平和を実現する人々は、幸いである、/その人たちは神の子と呼ばれる」。「神の子」、それは、神さまを信じる者のことです。平和を実現することに努めてまいりましょう。
(聖書から)
さて、お読みした聖書の言葉は、マタイによる福音書19章13節からです。新共同訳聖書では、13~15節までの言葉について、「子供を祝福する」という小見出しが付けられています。
13節をお読みします。
19:13 そのとき、イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れて来た。弟子たちはこの人々を叱った。
「イエスに手を置いて祈っていただくために」とありました。人々は子供たちを連れて来ました。それは、イエスさまに、子供たちの頭に手を置いて祈っていただくためでした。これは、イエスさまに、神さまの祝福を祈っていただくということを意味します。ところで、祝福とは何でしょう?祝福とは、神さまの恵みを受けるということです。もっと正確に言いますと、神さまの恵みを恵みとして受けるということです。私たちは、自分にとって良いことがある時は、神さまの恵みが与えられている、と考えます。こんな良いことがあるのだから、私は神さまの恵みによって生きている、と考えます。けれども、その反対の時はどうでしょう?私には神さまの恵みは与えられていない、と考えてしまうのではないでしょうか。
神さまの恵みを恵みとして受ける。それは、私たちにとって、幸せと思える時も、不幸と思える時も、どんな時も、神さまの恵みは変わることはない。神さまは私たちと共におられる。そのことを信じて生きるということです。苦しい時に苦しくなくなる。辛い時に辛くなくなる。そういうことはないかもしれません。しかし、その苦しみの中にあって、その辛さの中にあって、神さまは生きる力を与えてくださるのです。
私たちが、お互いのことを祈る時、祝福を祈るのではないでしょうか。教会に連なる兄弟姉妹、家族、友人、その一人一人に神さまの祝福があるように、と祈ります。どんな時にも、神さまの守りが、助けがありますように。神さまの力によって生きることができますように。私たちは互いのために祈ります。子供たちをイエスさまのもとに連れて来た人たちは、我が子を、イエスさまのもとに連れて行き、神さまの祝福を祈っていただこう。そういう思って、そう願ってやって来たのでしょう。ところが、その願いを妨げる者たちがいました。
「弟子たちはこの人々を叱った」。ここで「弟子たち」というのは、イエスさまの弟子たちのことです。彼らは、人々が子供たちをイエスさまのもとに連れて来て、神さまの祝福を祈ってもらおうとしたのに、それを妨げたのです。ここには、「この人々を叱った」とあります。「なぜ、子供たちをイエスさまのもとに連れて来たのか?ここは子供たちを連れて来るところではない!」そんな思いから、彼らを叱ったのでしょうか?
先日、日本バプテスト連盟の宣教会議がありました。神奈川県のある牧師先生が、こんな話をしておられました。「自分は、今まで礼拝というと、大人のための礼拝、子供のための礼拝というふうに、大人と子供を区別して、分けて考えていた。でも改めて、聖書を読み直してみると、大人だけの礼拝、子供だけの礼拝というのは本当にイエスさまが望んでおられることなのだろうか、と思うようになった。大人も子供もみんなで一緒に神さまを礼拝する、賛美する。それこそがイエスさまが喜ばれる礼拝なのではないだろうか?」そういう話でした。私はいろいろな礼拝の持ち方があってよいと思います。大人の礼拝、子供の礼拝、あるいは最近は外国の方々が増えてきましたから、外国の方が理解できるように、いろいろな国の言葉で礼拝を行うなど、いろいろな礼拝があってよいと思います。けれども、私たちは心を一つにして礼拝していきたいと思います。心を一つに、というのは、時間帯や場所は異なっていても、同じ主を見上げて礼拝するということです。私たちの教会では、今、朝の礼拝と夕の礼拝の二回行っていますが、朝の礼拝者、夕の礼拝者が心を一つにして、同じ主を見上げて礼拝していきたいと思います。
人々が子供たちを連れて来たことで、周りは賑やかになったかもしれません。ワイワイガヤガヤといろいろな声がする。すると、弟子たちは、何と不謹慎な、という思いになったのかもしれません。静かに、厳粛に神さまを礼拝する。それも大事なことでしょう。イエスさまは、弟子たちと人々のやり取りを聞いていたと思います。イエスさまは何とお答えになったのでしょうか。
19:14 しかし、イエスは言われた。「子供たちを来させなさい。わたしのところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。」
「しかし」とあります。それは、主の弟子たちとは違うお考えであったことを示しています。イエスさまはこのように言われました。「子供たちを来させなさい。わたしのところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである」。先ほど、弟子たちが子供たちを主のもとに連れて行こうとした人々を叱った、ということが書いてありました。これを文語訳聖書で読んでみますと、「弟子たち禁(いまし)めたれば」となっていました。この「いましめたれば」という言葉には、禁止という言葉の禁の字が使われていました。つまり、弟子たちは、人々が子供たちをイエスさまのもとに連れて来ることを禁止した、ということです。
ところが、イエスさまは「子供たちを来させなさい」とありました。これも文語訳聖書を見てみますと、「幼児(おさなご)らを許せ」となっていました。この「ゆるす」という言葉は、許可という言葉の許の字が使われていました。弟子たちは禁止した。しかし、イエスさまは許可したというのです。
弟子たちの判断というのは、ただ子供たちはうるさいから出て行け、といったものではなかったと思います。弟子たちなりに考えて出した判断だったと思います。イエスさまが福音を語られる。そこに騒いでいる子供たちがいたら、イエスさまの語ることを妨げることになってしまうのではないか・・・。いろいろと考えた上で出した判断だったと思います。けれども、弟子たちとイエスさまとでは、異なった考えでした。
私たちもこのようなことが度々あるのではないかと思います。決していい加減に考えたのではなく、本当にこれがよいことだと考えに考えた末に判断した。けれども、後になって、どうも違うようだ・・・。そんなことが数多くあるのではないかと思います。
何年か前に、銀座の国際フォーラムの中にあった相田みつをさんの美術館に行ったことがあります。相田さんの書かれた味のある文字と言葉が展示してありました。相田さんというと、「人間だもの」という言葉で有名です。一つ紹介します。
人間だもの、スーパーマンじゃないんだから。
人間だもの、コンピュータじゃないんだから。
人間だもの、神様でも仏様でもないんだから。
相田みつをさんの言葉を一つ一つ読んでみて、本当にそうだなあ、と共感することが多くありました。相田さんの言葉は、人間の本当の姿、本音、そういったことを言い表しておられます。私たち人間は本当に弱い、不完全な存在です。相田さんが言っているように、私たちは、神さまでも仏さまでもありません。それなのに、私たちは時に神さまのようになってしまうことがあります。自分の正しさを誇り、他人を裁いてしまう。それが罪ということです。イエスさまの弟子たちは、イエスさまのことを思って、考えて、人々を叱ったのです。でも、この時は、イエスさまとは考えが違ったのです。相田さん流の言い方をするなら、「人間だもの仕方がありません」ということになるでしょうか。ではその時、私たちはどうするでしょうか?自分の罪を、間違いを認めて、イエスさまにごめんなさい、と言うのです。このごめんなさい、これが、悔い改めということです。自分に向いていた心を神さまの方に向き直していく。そうやって、私たちは日々、悔い改めて、やり直して、出直して生きていくのです。
(むすび)
イエスさまはこう言われました。「子供たちを来させなさい。わたしのところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである」。私たちが気をつけなければならないこと、それは、イエスさまのところに来るのを妨げないように、ということです。何が妨げになるか?時に私たちの考えが、私たちの思いが、そして、私たちの正しさが、人をイエスさまのところに来ることの妨げになってしまうことがあるのです。イエスさまのところへ来ることの妨げではなく、イエスさまのところへどうぞ!そのために私たちはどうしたらよいでしょうか?
15節には、このようなことが書かれていました。
19:15 そして、子供たちに手を置いてから、そこを立ち去られた。
イエスさまは、子供たちに手を置いた。つまり、子供たちを祝福されたのです。イエスさまは、子供たちを祝福したかったのです。イエスさまがこの世においでになった。その目的は何だったでしょうか?ヨハネによる福音書10章10節の後半の言葉をお読みします。
10:10 わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。
ここには、「羊」とありますが、これは私たちのことです。今日の聖書の言葉には、「子供たち」とありましたが、これも私たちのことではないでしょうか。イエスさまは、私たちが命を、永遠の命を受けるため、それも豊かに受けるためにおいでになった、と言われました。イエスさまは、私たちを招いておられます。命を受けてほしい、永遠の命を豊かに受けてほしい。このイエスさまの心を受け止めて、私たちは、みんなでイエスさまのもとにまいりましょう。
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
神さまのみ子イエス・キリストは、私たちを祝福するために、私たちに永遠の命を与えるためにおいでになりました。主は「子供たちを来させなさい」と言われました。人々が、子供たちが主のもとに来ようとしている時に、私たちは、その妨げになりませんように。むしろ、主のもとに行くことの助け、支えとなりますように。「命の恵みを共に受け継ぐ者」(一ペトロ3章7節)でありますように。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン








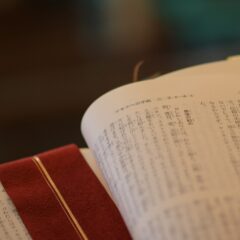

この記事へのコメントはありません。